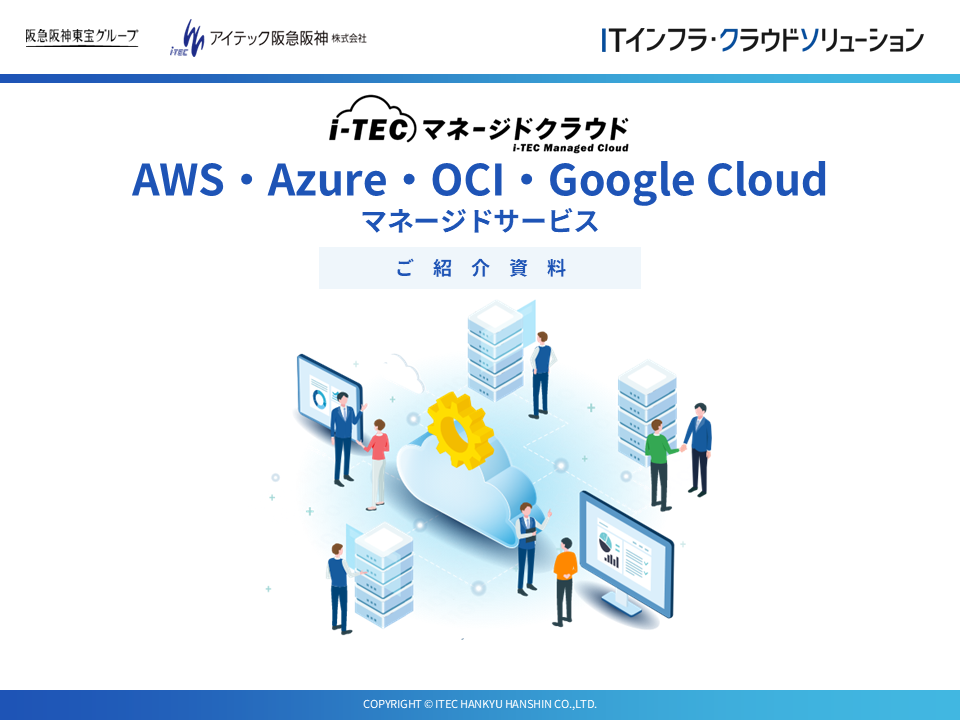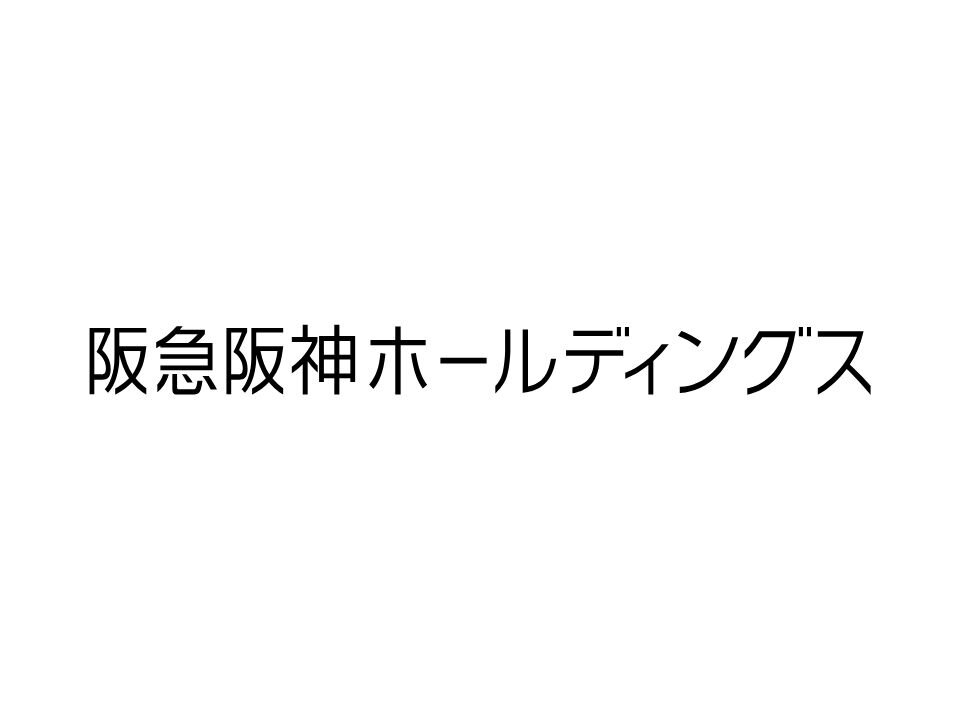コラム
2023-05-10
Amazon EBSとは?AWSのブロックストレージサービスの基本情報


アマゾンウェブサービス(以下、AWS)のAmazon Simple Storage Service(以下、Amazon S3)と同じストレージサービスである「Amazon Elastic Block Store(以下、Amazon EBS)」に関して、機能や特徴を解説します。
Amazon EBSとは?
Amazon EBSは、Amazon Amazon Elastic Compute Cloud(以下、Amazon EC2)とセットで使用することを前提に設計されたストレージサービスです。Amazon EBSはAmazon EC2とネットワーク経由で接続し、実行中のAmazon EC2のデータを保存するために使用されます。
Amazon EBSの主な機能
Amazon EBSの代表的な機能を紹介します。
スナップショット
EBSには「スナップショット」という、保存されたデータのバックアップを作成する機能があります。スナップショットは、ユーザーの任意のタイミングで作成することが可能で、保存先はAmazon S3です。
Amazon EBSのスナップショットは、増分バックアップ方式を採用しており、2世代目以降のスナップショットは直前のバックアップから変更された部分だけ保存されます。そのため、同じデータサイズのスナップショットを毎回取得する必要がなくなり、ストレージを効率よく利用することができます。
データライフサイクルマネージャー
データライフサイクルマネージャーは、上述したスナップショットの作成・保存・削除を自動化できる機能です。12時間もしくは24時間ごとの取得や、保持するスナップショットの世代数を指定して削除することができます。この機能を利用することで、運用を自動化することができます。
エラスティックボリューム
エラスティックボリュームは、Amazon EC2の稼働中にAmazon EBSのボリュームサイズの増加や種類の変更ができる機能です。かつては、Amazon EBSのボリュームサイズを増加するような場合、Amazon EC2を停止した上で一旦Amazon EBSを切断する作業が必要でした。しかし、エラスティックボリュームが実装されたことにより、ユーザーはAmazon EC2を稼働させたままでボリュームサイズを増加することができるようになりました。
マルチアタッチ
マルチアタッチは、同一アベイラビリティゾーンにある複数のAmazon EC2から1つのAmazon EBSに接続できる機能です。接続したAmazon EC2間でデータの共有が可能になり、共有ディスク型のクラスタ構成を組むことが可能となります。ただし、この機能は利用できるAmazon EBSの種類、Amazon EC2の種類、リージョンなどいくつかの制約事項があるため、確認した上で利用計画を立てる必要があります。また、Amazon EBS内のデータの一貫性を保つには、アプリケーション側で書き込み手順を常に保つ必要があります。
Amazon EBSのストレージタイプ
Amazon EBSのストレージは、大きく分けてSSD型とHDD型の2種類があります。ユーザーの用途に応じてストレージを適切に選択することで、Amazon EC2のパフォーマンスを向上させたり、コストを最適化することができます。
SSD型
I/Oサイズが小さく、データの読み書き頻度が高いシステム向けのストレージです。主な用途は、アプリケーションやデータベースなどです。
HDD型
I/Oサイズが大きく、高いスループットが必要なシステム向けのストレージです。主な用途は、アクセス頻度が低い大容量データの格納やログ格納などです。
Amazon EBSの特徴
Amazon EBSには以下の3つの特徴があります。
高い耐久性と可用性
Amazon EBSは、所属するアベイラビリティゾーン内で自動的に複製されるため、ユーザーが手動で冗長化構成を考える必要がありません。データが破損した場合でも、自動的に復元されます。また、99.999%の高い耐久性を誇ります。
高いセキュリティレベル
Amazon EBSに保存されたデータや、Amazon EC2からAmazon EBSへ転送中のデータを暗号化することができます。これにより、セキュリティレベルを向上することができます。
データの永続性
Amazon EBSに保存されたデータは、Amazon EC2の利用状況にかかわらず、永続的に保存できます。デフォルトでは、Amazon EC2の終了時に削除されますが、設定を変更することでデータを保存できます。
最後に
ここまで、AWSの代表的なストレージサービスであるAmazon EBSについて基礎的な内容を解説しましたが、Amazon EBSのように他のサービスやシステムと連携して使うことが前提とされるものは、用途に適した設定を行うにあたり専門的な知識や経験が必要な場合があります。
Amazon EBSの機能を適した形で利用できているか不安がある場合は、AWS Partner Network(APN)セレクトコンサルティングパートナーのアイテック阪急阪神にご相談ください。また、AWSの構築や運用をお任せできるAWSマネージドサービスもご検討ください。
関連資料をダウンロード
AWS・Azure・OCI・Google Cloudマネージドサービスご紹介資料
AWS、Azure、OCI、Google Cloudなどのパブリッククラウドの環境構築から運用までお任せいただけるマネージドサービスのご紹介資料です。