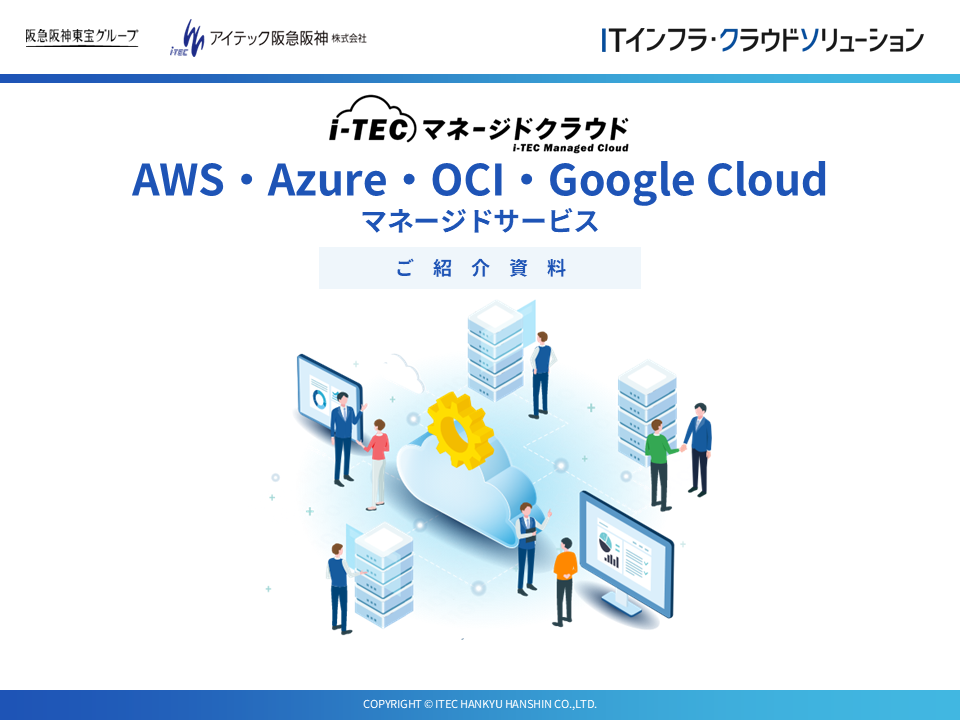コラム
2022-12-02
Amazon S3とは?3分でわかる用語解説


アマゾンウェブサービス(以下、AWS)の中でも特に利用される機会が多いAmazon S3に関して機能やメリットなどを解説します。
Amazon S3とは?
Amazon S3は、Amazon Simple Storage Service(以下、Amazon S3)の略で、Amazonが提供するストレージサービスです。Amazon S3を使用することでストレージのディスク管理や冗長化などを考慮する必要がなくなり、サービス開発など本来の業務に注力できるようになります。
Webサイトやアプリケーションなどのデータバックアップ先としての利用や動画・画像などの格納先としても利用されることが多く、既存のAWSサービスと連携させることで、非常に広範囲な使い方ができます。
Amazon S3の主な機能
Amazon S3の代表的な機能をいくつか紹介します。
バージョニング
Amazon S3に保存するデータはバージョニングという機能を利用すると、単一のデータであっても複数のバージョンを保持することが可能です。そのため、同じ名前のファイルを誤って上書きしたり、あるいは削除してしまったとしても以前のバージョンに戻すことが可能なため、簡単に復旧することができます。このように、ユーザー側の操作ミスにも配慮されている点は大きなメリットと言えます。
注意事項として、本機能はデフォルトで無効のため、バケットと呼ばれるいわゆるフォルダにあたるものを作成する際に有効化する必要があります。
ライフサイクル
Amazon S3のコスト効率化に役立つ機能がライフサイクルです。この機能により、Amazon S3内のデータの利用状況に応じてデータを自動で削除したり、安価なプランのストレージへ移動させるといったアクションを実行できます。
Amazon S3には、保存したデータへのアクセスパターンに応じて複数のプラン(ストレージクラス)が用意されています。例えば、保存されたデータがあまり利用されない状態にあるとします。この時、アクセス頻度が高いデータ向けのストレージクラスから、アクセス頻度が低いデータ向けのストレージクラスへ移行することにより、コストを抑制することが可能となります。
ライフサイクルを利用すると、保存してから一定期間を経過した古いバージョンのファイルを低アクセス頻度向けのストレージクラスに移行させる、などの制御を簡単に自動化できます。
また、一定期間を経過したら削除することも可能です。
静的コンテンツのホスティング
Amazon S3に保存したデータにはHTTPおよびHTTPSでアクセスできるため、Webサーバのように利用して静的なWebサイトを公開することが可能です。
通常Webサイトを公開する際、別途ホスティング用のサーバなどを用意する必要がありますが、Amazon S3を利用することでサーバや周辺ネットワークを構築する等の必要がなくなり、Webサイト運用担当者の負担を軽減することが可能です。
Amazon S3のメリット
Amazon S3利用には数多くのメリットがあります。今回は主要なものをいくつか紹介します。
容量無制限
Amazon S3には容量制限がなく、1ファイルあたり5TBまでであれば自由にデータをアップロードできる点がメリットとして挙げられます。
一般的なクラウドサービスにありがちな保存したいデータ容量を先に定めた上で運用するといったことを必要としません。現在の空き容量があと何GBなのか、容量確保のためにどれほどデータの削除をしなければならないのか、といった、ビジネスの拡大に伴うストレージ容量問題に悩まされる心配がなくなります。
高い耐久性、セキュリティ性
Amazon S3は保存したデータを複数のデータセンターへ自動的に冗長化をしてくれます。
また、99.999999999%(イレブンナイン)の高いデータ耐久性を実現できるように設計がされているため、万一の障害やエラー、脅威などからデータを保護できます。
基本的に、保存したデータは所有者のみアクセスが許可されているため、不特定多数にデータを閲覧、使用されることもありませんが、暗号化機能によりさらにセキュリティを強化することも可能です。
また、アクセス管理機能も備わっているため、データごとに個別のアクセス制限を設けることでセキュリティレベルをコントロールできます。
上記の特長から、機密性の高い重要な情報を管理することにAmazon S3は最適な環境であり、各企業におけるBCP(事業継続計画)対策やDR(災害復旧)対策に活用されています。
低い運用コスト
Amazon S3はAWS上の他のサービスと比較しても低価格で提供されています。そのため、オンプレミス環境で構築されるファイルサーバのように多くのストレージ容量を必要とする環境からAmazon S3に移行することでコストを削減することが可能です。
ただし、Amazon S3も他のAWSのサービスと同じく、利用した分だけコストがかかります。具体的には、保存されているデータ量、データに対するHTTPリクエスト数、データの転送量などによってコストが変動します。変動するコストに対し、自分の利用法が適切か否かを判断したい場合は、ストレージクラス分析という機能を使うことをおすすめします。この機能により、適切なデータ管理や移行タイミングなどを判断できるため、最適なAmazon S3運用が実現できます。
最後に
本記事では、AWSの代表的サービスであるAmazon S3について基礎的な内容を解説しました。
上述したとおり、Amazon S3を用いれば、低コストかつ容易にデータ管理が可能です。しかしながら、S3のような他のサービスやシステムと連携して使うことが前提とされるものは、詳細設定を進めるにあたり、専門的な知識や経験が必要となります。
Amazon S3の機能を十分に活用した自社環境の構築に不安がある場合、AWS Partner Network(APN)セレクトコンサルティングパートナーのアイテック阪急阪神にご相談ください。また、AWSの構築や運用をお任せできるAWSマネージドサービスもご検討ください。
関連資料をダウンロード
AWS・Azure・OCI・Google Cloudマネージドサービスご紹介資料
AWS、Azure、OCI、Google Cloudなどのパブリッククラウドの環境構築から運用までお任せいただけるマネージドサービスのご紹介資料です。